夏も本番。うだるような暑さに、たいしたことをしていなくても体力が奪われる日々。そんなとき、食べたくなるのが、にょろにょろ長い魚のアレ。
夏に元気をつけようという目的で、真っ先に思いつくのが、鰻(うなぎ)だ。かば焼き、串焼き、肝汁、とにかく鰻尽くしのコースと贅沢をきめてみたい。値段は張るが、食べると元気が出る(気がする)。鰻屋に行けば今や年中食べられるのに、なぜか夏の食べ物というイメージがあるのは、「土用丑の日に鰻を食べる」という習慣があるからだろう。そもそもなぜ、土用丑の日に鰻なのだろうか?
土用の丑の日には「う」のつくものを食べる
現代では、7月になり土用に入ると、鰻屋が忙しくなるので夏が鰻の旬と思う人が多いようだが、実は、そうではないらしい。江戸時代には、「秋の下り」といって川を下って海に産卵に行くころ鰻の味がいちばんおいしくなると言われていた。秋を待った方がおいしいのだから、夏は鰻屋に閑古鳥が鳴く。
江戸の町、ある夏のこと、営業不振で悩む鰻屋が懇意にしていた学者で智者の平賀源内に相談をもちかけた。江戸きってのコピーライター源内は、自筆で書いた「本日土用丑の日」という看板をこの店のおもてに掲げ、夏負けしないように鰻を食べようと呼びかけた。このアイデアで見事に繁盛し、他の鰻屋も次々と真似たという逸話がある。もともと土用丑の日に「う」のつくものを食べると夏負けの妙薬になるとかの習慣があり、これを巧みに利用した宣伝がまんまと成功したようである。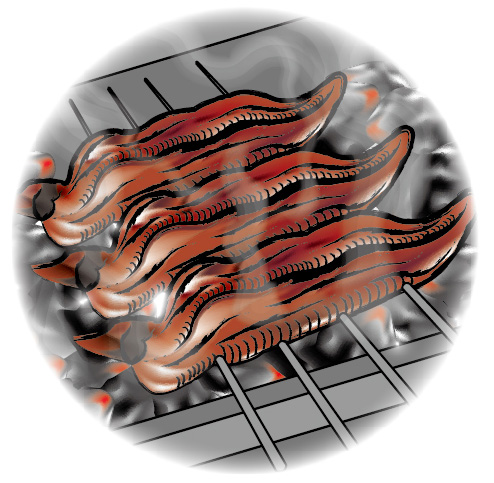
繁盛したといっても、鰻のかば焼きも庶民にとっては高嶺の花で、駕籠に乗るくらいの贅沢品だった。年中食べられるものではないのだから、暑くて体の消耗きびしい土用ぐらい鰻を食べて滋養にしたいという気持ちが広がり、人気化したとも言われている。土用であってもなかなか手が出ないという庶民に向けては、高価な鰻に代わって、アナゴやクワイのかば焼きがあったそうだ。
ふと思った。宣伝効果に乗せられてというこの逸話からすると、鰻は夏バテに直接の効果はないのだろうか?
調べてみると、鰻は、遠く奈良時代から“夏負けの妙薬”としてもてはやされており、「万葉集」にも記載があった。奈良時代の歌人として有名な貴族大友家持が、友人吉田石麿の痩躯をからかい、“痩せたる人を笑う歌”をよんでいる。
「石麻呂に 吾物申す 夏痩せに よしというものぞ 鰻とりめせ」(第十六巻 三八三五)
訳すと「石麻呂くんに言わせていただくが、夏痩せしているなら、鰻でも食べなさい」という感じだろうか。鰻はやはり、夏のパワーフードだったのだ。
鰻の食べ方東西事情
ところで鰻のかば焼きは、関西と関東で様子が違うということは、よく知られている。長細い魚なのでたいした違いはなさそうだが、気になるので調べてみた。
関西では、鰻を腹から割き関東(東京)では江戸以来背割りにされる。鰻を背割りにすると、身の側では腹壁膜が、皮の側では腹の皮の白いのが、中心になる。東京では「川魚は皮、海魚は身」ということわざの通り、鰻も皮の方から焼く。そうすると、身の中からじゅわっと脂肪が浮き出してくる。鰻屋の職人は、加減を見極めて、白焼きのままただちにせいろに入れる。ここにコツがあり、早すぎても遅すぎてもだめ。鰻をせいろに入れて蒸すのは身を柔らかくするためであるが、実は浮き上がった脂肪を流し去るという目的もある。
関西では、鰻を焼くのに、強い火で直焼きにしない。弱い火で身の方からゆっくりと焼き上げる。それゆえ鰻の脂肪は流れ出さない。だからせいろで蒸さないし、背割りの必要はない。(別冊歴史読本「食の歳時記」江戸・明治の味を訪ねて 新人物往来社)
東京の鰻に慣れた私は、関西の鰻のかば焼きは照り焼きのような感じがする(もちろんどちらもおいしいが)。どうやらはじめは西も東も腹割きだったが、武士が闊歩する江戸では「武士の切腹に通じる」ということで背割きになったという説もある。
鰻だけではない、にょろにょろ長い魚
夏になると、特に関西では鱧(はも)が登場する。京都市民などは鱧がメニューに上がると、夏が来たという気持ちになるそうだ。実は、私は鱧をよく知らない。
鱧を調べてみると、「本朝食鑑」に「うろこがなく、黒色で、斑点花文があり、鰻に頗る似ている」とある。鱧も鰻のような、うろこのないにょろにょろ長い魚であるらしい。暖海性の魚で、明石沖や瀬戸内海でよく捕れる西の魚で、関東以北ではほとんど捕れない。それだから江戸ではなじみが薄い魚なのだろう。関西では鯛(たい)に次いで、鱧をありがたがる傾向があるそうだが、その理由は、ちょうどこの原稿を書いている今開催されている祇園祭と関係あった。
鯛が祝い事につきものなら、鱧は祭りに欠かせない魚であり、一に鱧、二にも鱧である。毎年7月に行われる京都の祇園祭は、別名「鱧祭り」といわれるほど、祭りのごちそうは鱧が主役であった。大阪の天神祭も同じである。照り焼き、鱧ずし、吸い物などに使うが、身に小骨がたくさんあるのでその骨切りが大変で「鱧は一寸(33ミリ)を二十四に包丁する」といって、ほぼ一ミリ間隔に切れるとそれは名人芸であるといわれた。鱧は決して上等な魚ではなく、値段も安い。それが鱧料理になると高価になる。それは骨切りが大変だからである。(「江戸の魚食文化―川柳を通して―」蟻川トモ子)
鱧は水からあげても長時間生きられる強い魚なので、海から遠い京都でもよく食べられたそうだ。鱧料理は、京都の夏祭りと共にやってくる、熱さを乗り切るパワーフードだったのかもしれない。
江戸の深川ではどじょうを食べる。これも、夏になるとにわかに盛り上がってくるような気がすると思ったら、6月~8月が旬の魚であった。鰻ほど大きくないどじょうは、そのまま一尾食べることによって、たんぱく質をはじめ、日本人に不足がちなカルシウムの補給ができる、優秀な食材である。そのほか不飽和脂肪酸も多く含まれていることから、現在注目されている食材のひとつだそうだ。
驚くことに、江戸時代の人々にもこの滋養がわかっていて、当時どじょうには強精作用があると信じられており、井原西鶴の「好色一代男」(注)にも登場する。床の責道具の項に「さて台所には、生贄に泥鰌(どじょう)を放ち、ごぼう、山芋、玉子をいけさせ……」とある。精のつく食べ物であるがゆえ、夏バテ予防に鰻に代わってどじょうが庶民の台所で食べられていたと考えられる。
鰻、鱧、どじょう、夏バテ予防のパワーフードは、にょろにょろ長い魚が多い。この夏は、西も東も長いものに巻かれて、いや、長い物をおいしく食べて元気に乗り切りたい。
しかし、どうしても食欲がなく魚すら食べたくないときは、そうめんに限る。さっとゆでてきんきんに冷やしたそうめんを、ネギやみょうがなどの薬味と一緒にだしの効いたつゆで、つるつるつるっと喉に流し込む。
おっと、そうめんも、長い物ではないか!
(注)「好色一代男」浮世草子。八巻八冊。井原西鶴作。天和二年(1682)大坂荒砥屋から刊行。主人公世之介(よのすけ)の七歳から六十歳までの五十四年間のさまざまな好色体験を描く。全五十四章。
(文・黒川豆)
2014/7/22 更新


