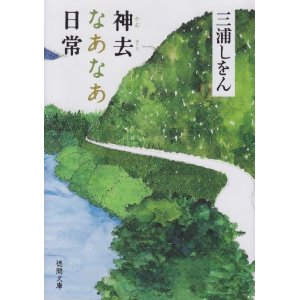三浦しをんさんの小説『神去なあなあ日常』が原作の映画「WOOD JOB~神去なあなあ日常」(矢口史靖監督)を観た。横浜で都会の高校生活をちゃらちゃら満喫していた平野勇気が、ひょんなこと(ここが小説と映画で設定が異なるのだが)から卒業と同時に山奥の神去村で林業に就くことになり、その奮闘を描いた物語。電車もバスもない、もちろんコンビニやゲームセンターのような娯楽などいっさいない村から、脱走を図るも失敗。虫もさわれない、沢の水も飲めない、ヒルに吸われてベソをかく勇気であったが、村で過ごす1年の間に、山村と林業の魅力に憑りつかれてたくましく成長していく、笑いあり涙ありのエンタテインメントである。
個人的に、この作品を単にエンタテインメントとしておさめることができなかったので、再度小説を読みなおした。平野勇気という青年と周りを囲む村人たち、神去村の珍事あれこれにはいい味がありすぎるのだが、今回はあえて、林業という仕事をテーマとして読んだ。何度読んでも、神去村には、独特のゆったりした空気が流れ、その地方の方言である「なあなあ」(ゆっくり行こう、まあ落ち着け)がしっくりきて、気持ちがいい。独特の空気や村の伝統文化・習慣、暮らしを作り出している背景には、村のほとんどを占める山と、住民のほとんどが従事する林業という仕事がある。
林業といってまっさきに思いつくのは、木を切る作業だろう。しかし斧やチェーンソーを使って伐倒するのは、林業の一部。勇気が3月に村に来てからの1年、雪起こし、植え付け、下草刈り、種取り、枝打ち、間伐、切出し、と様々な作業に従事している。林業って、こんなに作業があるのか! と、勇気と一緒に汗をかいてしまうくらいだ。かつては、これらの作業は分業であり、伐倒する仕事は木こり、切出しをする仕事は木挽きと呼ばれていた。今は林業の人手不足で同じ人間がすべてをこなすことが多い。これだけの仕事をしても、木の生産は100年単位。ということは、今日植林した木が出荷されるのは孫の代あたりだろうか。なんとも気長な話だ。そりゃあ「なあなあ」な感じで考えるようになるのは、当たり前かもしれない。
日本の森の変化と林業 ~おじいさんは山に柴刈りに行く必要がなくなった~
林業の仕事場となる日本の森は、この数十年で劇的な変化を遂げた。古来から日本では、森から暮らしに必要な炭や薪にする木材を採取したり、木の実や山菜といった山の恵みを食料にして暮らしを成り立たせてきた。昔話でおじいさんが山に柴刈りに行くのは当然。だって、柴を刈って来て適当な大きさに折ったり切ったりして、薪にして日々の燃料としていたのだから。また、山では、薪よりも軽くて火力の調整が簡単な炭を製造する炭焼きも盛んに行われていた。日本では、石器時代から炭が使用されていたと推測されており、平安時代には商品化されて年貢として徴収もされていたとのこと。ただし、炭を作るには非常に労力がかかるため一般に普及したのは明治時代になってから。炭の需要が最もあったのは1940年代で日本人一人当たり年間37キロ以上も使っていたという記録がある。その頃は、炭焼きという仕事も、森の仕事として最盛期を迎えていた。私の田舎新潟県の旧黒川村にも炭焼き小屋があり、私が子どもの頃は、近所に住んでいるおじいさんが、毎日小屋まで何キロも山道を自転車で登って通っていた。後になって、そのおじいさんが亡くなってから知ったことだが、彼が村の炭焼き小屋最後の職人であった。 日本では1950年代のエネルギー革命で、石油に取って代われた薪や炭は不要となり、60年代から70年代の高度成長期時代に建築用木材の需要が大幅に増大したことから、天然林を伐採して人工林に植え替える「拡大造林」が盛んに進められた。
日本では1950年代のエネルギー革命で、石油に取って代われた薪や炭は不要となり、60年代から70年代の高度成長期時代に建築用木材の需要が大幅に増大したことから、天然林を伐採して人工林に植え替える「拡大造林」が盛んに進められた。
人工林は手入れが必要だ。木材という“製品”を生産するために、その環境を整備しなければならない。1960年代の人工林は日本の森のうち26%ほどだったが、今は40%もある(『森と木と人の暮らし』農文協)。つまり、林業における作業は単純計算で1.5倍あるということだ。そこに来ての深刻な林業不振で、間伐ができず荒廃する人工林が後を絶たない。また、間伐しても木を運び出す手段がなくそのまま山に放置されてしまうこともある。昭和中期までは馬搬といって、馬で木材を山から里に運び下していた。馬もまた人の生活に寄り添っていた存在であったことは周知のことだろう。林業の馬搬では馬方という仕事が請け負うが、馬力からエンジンの動力へと移った(これまた)エネルギー革命以降、馬方も絶滅危惧の仕事となってしまった(岩手県遠野で馬搬技術継承に尽力している馬方たちがいるが、それば別の機会に紹介したい)。
消えかかっている日本の森の仕事
林業が危ういということは、林業の職場である山に住む人が減ってしまったことも要因のひとつである。確かに、過疎といわれる地域は、山間部が多い。では、なぜ人は山に住まなくなったのだろう。
それは「森の仕事」が徐々に消えてしまっていることと関係あるような気がする。仕事がない場所に現代人は暮らせない。「WOOD JOB」からさかのぼること数か月、「森聞き」(柴田昌平監督)という映画を観た。4人の高校生が4人の森の名人にインタビューをするドキュメンタリー作品だ。映画に登場する森の名人は、子どものころから畑と雑木林が循環する焼き畑を続けてきたおばあちゃん、綱一本で杉の大木に上り、良質の種を採取するおじいちゃん、合掌造りの家が立ち並ぶ世界遺産の五箇山で茅葺の屋根を葺くおじいちゃん、そして北海道の山で木を切り続けてきた木こりのおじいちゃん。これらの仕事は、ずっと昔から日本人が当たり前のように続けてきた森の仕事であり、日本から消えかかっている仕事でもある。
とくに印象に残ったのが、杉の種を採取するおじいちゃんのストーリー。綱一本を使い、器用に木に登っていく。木と木が近ければ、木の上からそのまま隣の木に飛び移ることもある(飛び移ることは神去村でヨキもやっていた)。今は、ムカデ梯子という梯子を使って木に登るのが一般的であり、勇気たち神去村の人たちも使っていた。ここに登場するおじいちゃんはこのやり方をする最後の人物であったが、高齢のため引退を宣言した。綱一本を使って杉の種取りをする仕事が、消えた。インタビューに来た男子高校生は、自分の目の前で、ひとつの森の仕事が日本から消えるのを目撃したのである。
森の中で行うアウトドアな仕事だけが森の仕事とは限らない。森の恵みを材料として仕事が成り立つ人々もいる。例えば、桶や樽職人。現代の生活に必要なバケツやボウル、洗面器といった容器は、昭和初期まで桶や樽を使っていた。桶や樽は鎌倉時代に登場し、昭和初期まで多くの職人が杉や檜を使って技を磨き、腕を振るっていた。ザルやかごも専門の竹細工職人がいた。材料のほとんどは竹で、日本の森には600種類以上の竹が自生しているので材料にはこと欠かない。「竹細工の善し悪しは竹の質で決まる」といわれているほど材料の選定は重要で、竹の年数や伐採の時期を1本1本竹の個性を見極めて作業をするのも竹細工職人の仕事だった。ところが、(またまた)エネルギー革命以降、バケツやボウル、ザルやかごは合成樹脂で作られるようになり、上記の職人たちの活躍の場がなくなってきてしまった。
現代を生きるわたしたちにできることは、どの地域であろうが人々が先祖代々森と共に生きてきた証しである、木でできた家や家具、桶や樽、ザルやかごなどに出会ったとき、「日本人の生活をずっと支えてくれてありがとう」という気持ちを持つことかもしれない。(文・黒川豆)

秋田には秋田杉を使った伝統工芸品としての桶を作る桶職人がいる(※注)
(※注)【HP】秋田の手しごと、暮らしごと「清水康孝 桶職人」より
2014/6/10 更新